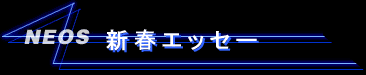
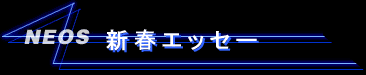
| ■ ナスカへの旅 ■ | ||||||||
| (株)東京システック 小 野 博 之 | ||||||||
|
夢の実現へ しかし、近年の旅行ブームの浸透はしごく簡単なパックツアーとしてこの遠い辺境の地も組み入れ、金と時間さえ準備すれば誰でもが容易に足を運ぶことの出来る地に変えていた。 さらに私の関心をいや増したのは、楠田枝里子のルポルタージュ「ナスカ砂の王国」(文藝春秋刊)や、ジム・ウッドマンの「ナスカ気球探検」(講談社刊)などの体験記である。 現在日本テレビの「世界まる見え!テレビ特捜部」の司会者として活躍中の楠田枝里子は、ナスカの地上絵の解明と保護に一生をささげたマリア・ライヘを訪ね、単身この地に何度も足を運んでいるばかりか、東西封鎖の状況下マリア・ライヘの生まれた東ベルリンにまで赴き軌跡を追っている。その地道な努力と情熱は、テレビタレントとしての彼女のイメージとはちょっと結びつきにくいが、私にとって感銘の一書であった。 ジム・ウッドマンは古代ナスカ人が気球に乗って地上絵を見ていたことを確信し、自らそれを実体験して見せた。ナスカ人は現代の技術も及ばない高度な機織り技術によって、気球の空気を逃がすことのない目のつんだ布地を織っていた。また気球に吊り下げ、人間を運ぶに十分な強度と軽さを備えた材料としてチチカカ湖に生えるバルサ材がある。彼は古代人が使ったと思われるこれらの材料によって、同じ形体の気球を造ってナスカの砂漠の上を飛んで見せた。その着想から現実に至る物語は壮大で感動的だった。 書物に記録された気球による飛行の創始者は1783年、フランスのモンゴルフィエ兄弟となっている。しかし、ウッドマンはそれより74年も前の1709年にブラジルでバルトロミュー・グズマンという人物が気球に乗ったことを突き止めている。その事実の延長として、古代人も気球乗りの技術を持っていたのではないかというのが彼の発想と冒険の原点となった。それは地上絵の謎に迫る挑戦でもあった。 そんなわけで、私のナスカへの憧憬はより大きなものになっていたが、昨年還暦の記念に「世界サイン紀行」第2巻の発刊を思い立ったとき、この地上絵をページに是非加えたいと思った。以前私はトルコの古代都市の舗石に掘られたサインから世界最古のサインに関心を持ったが、それと対比する意味で世界最大のサインをあげるならば、このナスカの地上絵をおいてないと考えた。そのことで、ナスカに旅することは私の緊要の課題となった。 郷に入っては郷に従え 私の選んだツアーは、前日にクスコに泊まり翌早朝飛行機でリマに行くことになっていた。クスコ発が7時30分でリマ着が8時30分だから、それから乗り継いでナスカに向かえば、まあまあなんとか午前中には地上絵を目にすることが出来るという計算であった。 ところが計画通りには運ばないのが旅というもの、ことに南米ペルーにおいてはそれが常識。まずクスコからリマに向かう便が1時間遅れ、リマの空港でジリジリしながら乗り換えのナスカ行きを待つこと更に1時間半。やっとナスカに着いた時には時計はもう12時半を回っていた。「地上絵観光の飛行機は30分待ちです。それまでに昼食をするには中途半端ですから、その辺の観光を先に済ませましょう」と添乗員が言い出し、肝心の地上絵との邂逅は限りなく条件の悪い時間帯にズレ込んでいった。こうなれば「郷に入っては郷に従え」の精神でじっくり構えるしかないだろう。観光がそんな30分程度ですむわけがないだろうと思っていたが、なしにろ砂漠の真っ只中の小さな町。ちょうど3、40分たった頃、空港の車が「3人だけ先に乗れます」と迎えに来た。 これを逃したらもう地上絵に遭えないような気がして必死に手を挙げた。私と一緒に先発を志願したのは2人とも単身参加の中年女性。最近の女性上位傾向は海外旅行にもはっきりと現れていて、どんなツアーでも女性の参加者が男性に比べ圧倒的に多い。独身者ばかりでなく既婚の女性もダンナに留守番役をさせてどんどん参加している。しかも好奇心旺盛でエネルギッシュ。リオのサンバショーで、外人を尻目に真っ先に舞台に出て踊り出したのが我がツアーの女性陣であった。 スタンバイ
空港で待機していたのは4人乗りのセスナ。操縦士を除けば3人の貸し切りというわけで、これは好都合。小さい方が小回りがきくし、より地上に接近して飛んでくれそうに思ったからだ。はやる心で機に乗り込んだら、前方計器盤の上に「チップありがとうございます」と、たどたどしい日本語で書かれた紙が貼り付けてある。これでは強要されたも同然、渡さないわけにはいかないだろう。日本語でしか出ていないところを見ると、ここでも日本人が大得意なのだろう。手術する患者をもつ家族が少しでも丁寧に診てもらいたい一心で謝礼をはずむ心境と同じで、手抜きされては大変、ちょっとばかりはずんで渡せば大男の操縦士はニッコリ。
地上絵の上を飛ぶのは約15分。そこまでの道中に15分を要するが、早くもカメラを手にスタンバイの体勢に入る。電池よし、作動設定よし、万全である。肝心な時にフィルムが切れては大変と、撮影途中のフィルムも新しいものと入れ替える。眼下には視界の届く限り砂の山また山が連なり、こんな過酷な自然環境の中よくも人間が住んでいたものと感心しきり。ときに干上がった大河の跡のような光景が遠望され、こんな砂漠に河が流れていたいたとも考えられず不思議に思った。風景はそのうち砂漠の平地に変わるが、その中にパンアメリカン・ハイウェイの一本の線が人為的な唯一の証としてかすかに見え隠れするようになる。 始めに現れた地上絵は「宇宙人」または「宇宙飛行士」と名付けられているもので、砂山の斜面に描かれた子どものイタズラ描きのような、丸い目をした人間の像であった。ナスカの地上絵は全て一筆書きの要領で交わるところのない1本の線で描かれているのに、これだけは例外的にそうなっておらず、また斜面に描かれたのもこれ一つである。 操縦士が新しい絵が現れるたびに「ク・モ」「サ・ル」「コ・ン・ド・ル」と大きくカタコトで話しかけ、われわれが確認するまでその上を旋回してから次の絵に移動する。
幸い心配された風はなく、晴れ上がった空の下、ほとんど白色に近い乾いた砂漠の砂地にそれらの絵ははっきりと見分けることが出来たが、説明されなければそのまま通り過ぎたかもしれない。というのも地表には絵とともに無数の直線が入り乱れて走り、時に車のわだちらしきものも加わるからだ。それは感動的な光景であった。一つ一つのデザインが素晴らしい。描画は簡素で古代人が描いたとは思えないほど洗練されている。しかし、絵にジッと見とれているヒマはない。 アクシデント
15分の見物時間はアッという間に経ってしまった。とても全部の地上絵を見ることは出来ず、心残りを抱きながらも見ることの出来た満足感もひとしおであった。地上絵とともに印象的だったのは数知れない真っ直ぐなラインの交錯である。ここが宇宙人の飛行体の発着地であったという荒唐無稽な説もあり、なるほどとうなずかされた。ことに、緩やかな台形状に突出したスロープの平面に印された長大な二等辺三角形を目にしたときは奇妙な思いがした。その形体はまさにロケットの発射台そのものといった感じなのだ。 昼食にありついたのは午後3時過ぎであった。場所はホテル・ツーリスタのプールサイドのベランダ。手入れの行き届いた植え込みと芝生の向こうに白いバンガロー風の宿泊棟が点在し、別世界のように美しい。 この素晴らしいホテルにはマリア・ライヘが研究室として一室を提供され、亡くなるまで住んでいた。食事をしたパーゴラの下は、楠田枝里子がマリア・ライヘから幾度も話を聞いた場所でもあるのだ。飛行の感動覚めやらぬ上に、私はそんなシーンが胸に浮かんできて感慨ひとしおであった。 地上絵の謎 古代のナスカ人が何ゆえに苦労を重ねこんな地上絵を描いたのか、その真意はいまだに謎であるが、諸説の中でマリア・ライヘやその師となったアメリカの歴史学者P・コソックが唱えた「世界最大のカレンダー」説が最も有名である。太陽の運行と刻まれた直線の方向が一致し、描かれた絵は星座を表したものというのがその解釈であるが、この説には批判も多い。印された線は無数にあり、そのうちの1本が夏至の太陽が沈んだ方向と一致しても何ら不思議はない。 一筆書きの要領で描かれた地上絵は、1本のネオン管が形作る模様と共通していて興味深い。何故に一筆書きなのか。何故に交わる線がないのか。そこにこの絵の秘密がかくされているように思われる。 6年前であるが、テレビ東京が開局30周年を記念して「蜃気楼の王国」というドキュメント番組を放送した。これは古代の巨大文明には全て蜃気楼が影響しているという、イタリアの自然学者ヘルムート・トリブッチの説をテレビ化したものであるが、私には実に興味深かった。
彼の説によるとナスカの地上絵もその例に漏れない。砂漠には蜃気楼がつきものである。ナスカの古代人もこの蜃気楼を見ているはずである。砂漠の住人にとって水は生命の根幹であり、水辺の風景を映し出した蜃気楼は、人々に羨望と脅威を抱かせたことだろう。当時の指導者たちがその蜃気楼を見て、水乞いの儀式を行ったことも容易に推測される。地上絵に描かれた動物や植物は全て水に関係するものばかりであり、この絵の中に砂漠に降りる「天の水」を呼び入れようと祈ったというのが、トリブッチの説である。一筆書きの絵模様は全て端部が閉じてられておらず、その説の裏付けとしている。更に興味深いのは、クモの絵では一方の端部にクサビ状の三角形が添えられていることだ。彼はそれを誘い入れた水を逃がさないための弁と解釈する。トリブッチの著書「蜃気楼文明」を読み、その壮大な論拠を知るとなるほどと、うなずかざるを得ない。しかし、無数の錯綜するラインや長大な二等辺三角形の目的についてまだ十分に解き明かされてはいない。 地球上にはこんな不思議がまだ沢山残されている。だからこそ面白いともいえるのではなかろうか。 |
||||||||