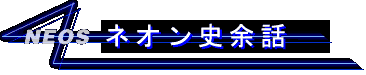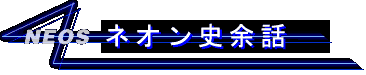|
われわれにも縁の深い(社)照明学会から当協会に学会誌の今年4月号にネオンとイルミネーションを特集として扱いたいから執筆協力願いたいと言って来たのは昨年の11月のことであった。協会では十数年前、ネオンの騒色公害が世間の話題になりだしたことで「ネオンの光の見え方」に関する調査研究を照明学会に依頼した経緯もあり全面的に協力することとなった。在京理事のうち「ネオンサインの知識と実務」の執筆に当たった人たちが中心になって担当することになった。
依頼された内容は「アピールする光」のテーマのもとに「ネオンサイン・イルミネーションの歴史」に始まり、「表現方法」「発光原理と点滅制御の仕組み」「施工技術」「工事資格と関連法規」「環境問題と今後の課題」とかなり総括的な項目が並び、総ページ数36ページにわたる比較的大部なものであった。私はこの際ネオンの歴史を勉強し直すのも良かろうと考え、その項目の執筆を担当させてもらった。
とは言うものの日本のネオン史の参考資料としては、わがネオン協会が昭和52年に刊行した「日本のネオン」と井上晃氏作表による「ネオンサイン年表」程度しかない。井上晃氏はウララネオンに長く在職された方だが「日本のネオン」でも相当部分を執筆されているようだ。ネオンの発明にいたる経緯ではルディ・スターン著「THE NEW LET THERE BE NEON」にかなりのページを割いて触れていたのが大変参考になった。
今回痛感したことは、いまや協会編纂の「日本のネオン」が業界にとって、いかにかけがえのない貴重な資料となっているかということだ。日本でのネオンの誕生から高度成長期にいたるまでとオイルショック時の対応が詳述されていているばかりか、ネオン技術の変遷やこぼれ話までよくもこれだけのデータが集められたものと思う。この本は高村五郎名誉会長が副会長時代に編纂委員長となって刊行したものである。実際に執筆に携わった方々はもはや全員鬼籍に入られていることだろうが、大変なご苦労があったことがしのばれる。現在、この本に記載された事実について直接知る人もほとんどなく、本書なくしては貴重なネオンの史実が闇に埋もれてしまったことだろう。本に収録された写真や図版にしても、どのように入手されたものか、現在それらの資料はどうなっているものか、再びそろえることは難しいのではなかろうか。私の執筆原稿もこの「日本のネオン」に頼るところが大きく、添付写真も直接この本からとらざるを得なかった。
執筆に当たってはいろいろ疑問に思われる点が出てきて、歴史の不確かさについて考えさせられたり、思わぬ発見があってほくそえんだりした。そのあれこれについて記してみたい。
先ず、わが国で初めてネオンが点いたのは大正7年(1918年)、東京・銀座1丁目の現在でもある谷沢カバン店であると「日本のネオン」に書かれていて、そのことは業界人周知のことではあるが、執筆に当たってハタと疑問が生じた。この店は果たして今でもあるのだろうか。
当協会の事務所が数年前まで銀座にあったことから私もこの界隈はよく通ったが、谷沢カバン店をその気で確認したことはなかった。本が書かれてから既に25年間が経過し、バブル崩壊という激変の時代を経過している。万一にももう無くなっているとして「健在」と書いてはウソになる。ここは改めて確認する必要ありと思い、所要のついでに探してみたら、それがちゃんと実在していた。カバン店というよりは輸入ブランドもののバッグ屋さんといった風な高級店で、間口は狭いながらも全面ガラス張りのファサードに「GINNZA TANIZAWA」とだけ書いた、しゃれたサインが付いていた。
さて、ジョルジュ・クロードがネオンサインを発明し、公開したのは1910年のパリ万博においてという、これまでの認識は間違いであり、1910年にはパリ万博は開催されておらず、公開はパリの政府庁舎グランパレスにおいてであったことは私が折々に言ってきたことでもあるが(NEOS Vol.23参照)、それではクロードが現在のネオンのどこまでを発明したのかについては「日本のネオン」は触れていない。この点ではルディ・スターンの前掲著書に詳しい。実はグランパレスにおける初公開もこの本の記載によって知った。
クロードはネオンガスによる赤色に加えてアルゴンガスを使った青色の点灯にも成功しているばかりか、ガラス管の内側を塗料でコーティングすることによっていろいろな色を出す色管の製法も発明している。いわば現在にいたるネオンサインの基本原理のほとんどが彼によって確立されたことになる。
当時は病院や酸素アセチレン溶接用に酸素の需要が多く、彼は安価で高品質な酸素の製法の実験過程でネオンの発光現象を発見している。
グランパレスはパリのコンコルド広場と凱旋門を結ぶシャンゼリゼ通りに面する壮麗な建物で現在美術館になっているが、中央の大ホールが全面ガラス張りの天井になっていて見事である。鉄骨部分に優雅なアールヌーボー式装飾が施されていて初期の鋼材加工にもデザイン精神が豊かに盛り込まれていたことがうかがえる。世界初のネオンサインが輝いた、こんな建物が現存することは感慨深い。パリ訪問の折りには是非立ち寄って内部を実見されることをお勧めしたい。
世界で初めてネオンによる広告サインが登場したのは1912年のこと。「日本のネオン」によればパリのモンマルトル通りにあるクワフェール宮殿にてとなっているが(48頁参照)、ルディ・スターンの著書では同名の小さな理髪店と書いてある。さて、どちらの説が正しいものかと思案したが、宮殿に広告ネオンというのはちょっとどうかということで私の文ではルディ・スターンの記述を採用した。しかし、宮殿と小さな理髪店では大違い。一体どうしてこのようなことになったのか不思議に思ったが、英語に堪能な当事務局の加藤局長が種明かしをしてくれた。ルディ・スターンの本の原文は「a
small barber shop called Palais Coiffeur」となっているがクワフェールCoiffeurは固有名詞ではなく、理容師もしくは美容師を意味する。つまり、「理容師の宮殿」というのが理髪店の店名であり、「日本のネオン」は理容師Coiffeurを宮殿Palaisの名称と解釈してしまったわけだ。
ところで、クロードはその後1915年に腐蝕に対して高い耐久性を持つ電極を開発し、特許をとるとともにクロードネオン社を設立した。彼は優れた科学者であり発明家であるばかりではなく、精力的な事業家でもあったようだ。クロードによるネオンがアメリカにおいて急速な発展を遂げた理由にはそれまでアメリカでかなりの普及をみていたムーア管による点灯技術より格段に優れていたことも然りながら、クロードネオン社がフランチャイズシステムによってアメリカの多くの地方都市に提携店を設けたことによる。それによって一大クロード帝国を築くが、その後1932年に主要な特許が失効しクロード社の優位は終った。
「日本のネオン」ではわが日本のクロードネオン電気会社(以下「旧クロード社」)が「ジョルジュ・クロードの可変式漏洩変圧器を以って、放電管に供給する特許を譲り受けた」と記してあるが、クロードはそんな技術まで開発している。図らずもこの特許権問題が業界を挙げての係争事件に繋がり、戦前の組合結成の端緒ともなったことは興味深い。それは昭和7年(1932年)のことであり、その同じ年にクロードネオン社の主要特許が失効していることも歴史の皮肉というべきか。
この係争事件について「日本のネオン」は一項目を割いて詳しく述べているものの、今となってはなんとも判りにくい。多分に筆者自身の身びいきもあったようで、この件について一方の当事者でもあった大阪クロード(株)の喜多河育造氏が平成10年のNEOS盛夏号(Vol.48)で反論を寄せられている。それによれば、一審「旧クロード社」の勝訴、二審敗訴となり最高裁に持ち込まれたものの、大東亜戦争間近の昭和16年、ネオンの点灯禁止令が出るに及び、そんな係争どころではなく、両者痛み分けとなったとのこと。しかし現時点で考えてみれば、「旧クロード社」一社を除きネオン業界全般がジョルジュ・クロードの特許を犯すことなく技術の恩恵に浴せたことこそ不思議な気がする。
ネオン以前はイルミネーションが夜空の主役だったわけであるが、このイルミネーションの歴史でも不可思議なことがある。
ルディ・スターンは「1900年、ニューヨークで建築された初期の高層ビルであるフラットアイアン・ビル壁面に取り付けられた電球文字が大型屋外広告の始まりとなった」と述べている。これは高さ15m、幅25mにわたってサイン文字を連ね、1457個の白熱球が使用されたとのこと。「フラットアイアン・ビル」は現在もある。超鋭角の三角形平面をしていて、まるでフラットなアイロンのように見えるところからこの愛称で呼ばれ、いまでもニューヨークの名物ビルの一つになっている。ところが、建築史の上でも貴重な存在であるこのビルの竣工は1902年のはずである。スターンの本には写真も添えられているが、ビルの形状は現在のものとは似てもつかない。フラットアイアン・ビルの名称で呼ばれるビルがもう一つ在ったとは考えにくい。事実は不明ながら、こんなミスを発見したことも今回の小さな収穫であった。
過去の歴史を掘り起こすことは容易なことではない。現在、都市の夜空に輝くネオンも20年後、30年後には消えてしまい、遠からず人々の記憶からも忘れ去られてしまう。先人たちがそんな記憶を呼び覚ます努力をしてくれたように、われわれにはネオンサインを貴重な文化の遺産として記録にとどめる責務があるのではなかろうか。
|