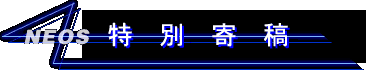
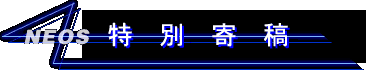
| ■ 小津映画で発見したこと
■ 理事 小野博之 |
||||
| 小津映画を再評価する 昨年は日本映画の世界的名匠小津安二郎の生誕100周年に当たるとのことで、年末から正月にかけて小津作品のテレビ放映が盛んだった。小津監督は1903年12月に生まれ、63年12月に60歳で亡くなっている。その間の監督作品は1927年(昭和2年)から1962年(昭和37年)までの36年間で計54本。内プリントが現存する作品は37本でそのすべてがNHKのBS2で放送された。そんなことで、この正月休みはそれらの作品を追いかけるのに忙しかった。初期のものは無声映画でその後白黒トーキー、カラー、ワイドと映画史をたどるほどの幅があるが、そのうち私が映画館で観たのはカラー化以降。そんなすでに観た作品も40年も経過すればほとんど忘れていて全作品を新鮮な気持ちで鑑賞することができた。 懐かしい質素な社会 私がとくに共感を持って観たのは昭和20年代後半から30年代前半の作品だが、それは私の青春と時代が重なるからに他ならない。高度成長期直前のまだ質素な社会であった。そのころの時代背景もそうだが、もう忘れていた生活描写が面白い。お櫃、足踏みミシン、火鉢、ねこコタツなどの生活小道具が懐かしい。隣近所で呼び出してもらう電話や、緊急時の電報もそういえば昔はどこの家もそうだったなと記憶がよみがえる。「早春」ではビールの栓を抜くときに栓抜きでコンコンと王冠を叩くシーンが出てきたが昔はみんなそうしていたものだ。電気冷蔵庫のない時代、水で冷やしただけのビールは生ぬるく泡が多い。王冠を叩くと泡が出にくくなるというのがその理由と聞いたが、いまとなればそんな迷信をよくもみんな本気にしていたものだ。「お茶漬けの味」では海外に出張する主人公をみんなが羽田空港で見送るシーンがあるが、テラスでいっせいに手を振る風景が懐かしい。あのころはパチンコが既に大衆娯楽の花形だったと見えてパチンコ台で玉をはじくシーンがよく登場する。玉を一個ずつ穴にねじ込む式に、あわただしい現代とは一味違う時間の流れが感じられる。 意外なサインの効用 小津安二郎は東京、深川の生まれで、そのせいか映画の舞台はそのほとんどが東京である。題名に東京がついたものも有名な「東京物語」以外に「東京の合唱」「東京の女」「東京の宿」「東京暮色」と多い。映画の背景に出てくる東京の町並みはほとんどがロケによる実写で、あのころの風景が偲ばれる。それと同時にネオンサインや看板がよく映されているのも小津映画の特徴である。「彼岸花」(昭和33年)では銀座のシーンでビクターの大きなネオン塔が晴れやかに出てきた。そんなシーンを拾っていけば銀座のネオン史になるのではなかろうか。そればかりか、彼の映画ではしばしば場面転換のたびにサインが出てくる。つまり、物語の舞台が変わったことをサインで示しているのだ。
その代表的な作品は「東京暮色」(昭和32年)だ。原節子、有馬稲子の二人の姉妹と笠智衆の父親だけの片親家族の物語である。母親は男と駆け落ちし、今はまた別の男と麻雀屋をやっている。妹の有馬稲子は不良仲間と付き合って妊娠しているが結局は捨てられ、そのために自殺する。この映画に登場する看板だが、笠智衆が立ち寄る池袋の小料理屋「お多福」、鰻屋「う」、出て行った母親、山田五十鈴が経営する五反田の麻雀屋「壽荘」、有馬稲子が付き合う男のアパート「相生荘」、彼女が腹の子供を下ろす産婦人科「笠原医院」、それに待ちぼうけを食わされるバー「Gerbera」、喫茶店「エトアール」、ラーメン屋「珍々軒」とかぞえただけでも八つの看板が場面の転換とともに入れ替わり立ち代り登場するのだ。面白いことに大きく「う」とだけ書かれた鰻屋のスタンド看板が「秋日和」にも登場するし、「珍々軒」という屋号の店が出て来る作品をほかに二つ見つけた。小津安二郎という監督はサインに特別のこだわりを持っているようである。 不二ネオンの石柱 小津映画の中でも最も有名で評価の高いのが「東京物語」(昭和28年)だが、この映画の中で私は実に興味深い発見をした。東京で生活している息子や娘を訪ねて尾道から出てきた老夫婦の笠智衆と東山千栄子が、自分たちの生活に忙しくろくろく相手にもなってくれない子供たちに接し、早々に帰っていくことになる。両親の世話で困った長女の杉村春子は妙案を立て二人を熱海に送り出すが、老夫婦は宿で落ち着けず翌日帰ってきてしまう。迷惑気味な長女に二人はそれぞれにその夜泊めてもらう知人を求めて家を出る。
そのとき上野公園で時間つぶしをするが、そのシーンで私はハッとした。二人が腰を下ろして一休みしたのは大きなお寺の門前だが、御影石の角柱が並んだ格子塀には一本一本寄進者の名前が彫り込んである。ほんの一瞬流れた風景の格子の一本にネオンと言う文字が読み取れるではないか。漢字の名前が並ぶ中そこだけカタカナだからよく目に付く。しかし、ネオンの上がちょうど画面の切れ目に当たっていてよく読めない。その頃上野に近く会社を構えていた同業者とはいったいどこなのだろうか。関心が深まり、さらに録画したものを何度も繰り返して見た。すると意外なことに今まで切れていた上端が少し多く見えるときがある。さらに静止画像にしてよくよく見れば、ネオンの上に不二という漢字が判読できる。不二ネオンは戦後、業界に名が聞こえた会社である。今はもうないが、そんな会社が小津作品の中に名を残していようとは驚きだった。この会社は根岸にあったが、そこから近い上野の寺の檀家として石塀の造作に寄進したことが容易に想像される。しかし、そんな事実を映画の中で発見しようとは、私にとってはまさに天文マニアが広い夜空に新彗星を発見したような思いであった。 |